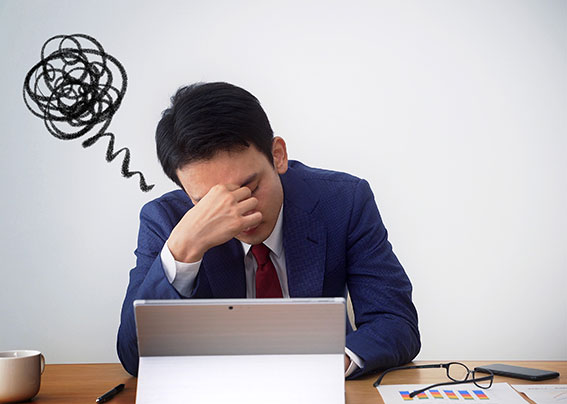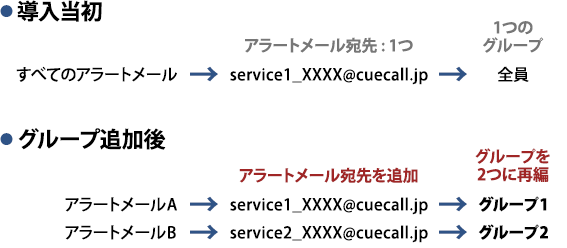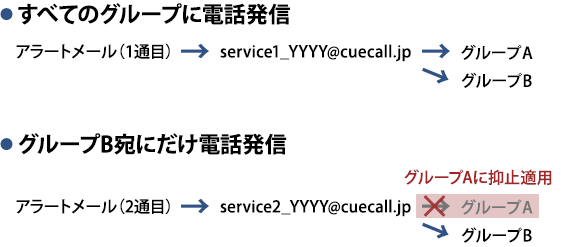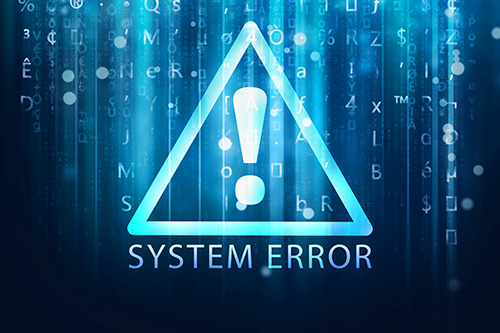業務効率化のアイデアをご紹介!メール受信を電話通知すると効率的!?

「業務効率化」とは、「ムリ・ムダ・ムラ」を見つけて排除し、より効率的に業務を行うための取り組みです。非効率な状態のままビジネスを続けていると、売り上げが頭打ちになり、会社の成長もストップしてしまいます。今回は、時間的・経済的なコストを削減することで、業務効率化させるアイデアや業務効率化に役立つ便利なツールについて、ご紹介します。
特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」
詳しくはこちら
1. 業務効率化になるアイデア

業務を効率化させるアイデアには、大小さまざまなものがあります。日々のルーティンを工夫するだけでも、業務効率化を行うことは可能です。以下で、経営層レベルや部門・チームレベルなど、会社におけるポジショニングレベル別に業務効率化のアイデアをご紹介します。
経営レベル
まずは、経営レベルでの業務効率化を実現する手法をご紹介します。
- 会社全体での目的を定める
- 優先順位を決める
- 決裁権を分散する
- 制度・体制を変更する
自社のビジネスが目指す最終目的を明確に定めることで、会社が進むべき道筋がはっきりし、おのずと業務効率がアップします。さらに、トップダウンで業務の優先順位をつけることで、社員が安心して自分の仕事に集中できるようになります。その上で決裁権を分散させてボトルネックを防ぐことが、業務効率を上げるためには重要です。また、目的を達成するために必要な制度や社内人事体制を整えることも大切です。
部門・チームレベル
部門・チームレベルでの業務効率化を実現するアイデアは、次のようなものです。
- 情報・ナレッジを共有する
- 担当を変更する・アウトソーシングを利用する
- システムを導入する
- 優先順位を決める
- 期限を決める
部門・チームレベルでは、業務の内容を見直し、情報やナレッジを共有することが大切です。その上で、担当を見直し、最適な配置にすることが肝要です。場合によっては、アウトソーシングなど外部の人材を活用することも、業務効率化につながります。さらに、手作業で行っていたものを、システムを利用して自動化することで効率化を図れます。
また、業務の優先順位や提出期限を決めることは、非常に重要なことです。特に新人や若手など、仕事の内容を把握して優先順位を決めることが難しいメンバーがいる場合は、先輩社員やリーダーがフォローアップし、チーム全体で業務効率を上げていくようにしましょう。
実務レベル
実務レベルでの業務効率化になるアイデアは、次のようなものが挙げられます。
- 業務マニュアルを作成する
- フォーマットを統一する
- データベースを活用する
まずは、業務マニュアルを作成し、現在行っている業務に無駄がないか、改善できるところはないかを確認します。業務マニュアルを作成することで、担当者の不在時に代わりに対応することができたり、担当者の変更の際に引継ぎがスムーズに行えたりするというメリットもあります。
実務レベルでは、実際に作業を行う際に、あらかじめ用意したり、揃えておいたりすると業務効率がアップするものがあります。必要な書類のフォーマットを統一しておく、データベースを活用するというのは、その一例です。フォーマットを整え、データベースにデータを蓄積しておくことで、数値化や見える化がしやすくなります。また問い合わせなどの情報を記録しておくと、再度問い合わせがあったときにも、すぐに内容が把握できて便利です。実際に行う業務の中で必要なものを検討してみましょう。
個人レベル
個人レベルでの業務効率化を実現するアイデアは、次のようなものが挙げられます。
- ショートカットキーを使いこなす
- よく使う固有名詞を「辞書登録」する
- 確認をこまめに行う
- 時間を決めて行動する
- 適度に休憩をとる
個人レベルでは、PC作業を改善することで、作業時間を短縮できます。一例として、ショートカットキーの活用、辞書登録機能の活用、ショートカットアイコンの設置などが挙げられます。ちょっとした改善のように思えることでも、毎日何度も行う作業のため、1ヵ月・1年という長期のスパンで考えると、かなりの業務改善になります。
業務を行う上では、確認をこまめに行うことも大切です。最後まで作業をしてから確認をしたところ、方向性が全く違って、最初から作業をやり直すことになるのでは、業務効率は大変悪くなってしまいます。作業の合間合間で上司やクライアントなどにこまめに確認を取り、こまめに軌道修正できるようにしましょう。また、時間を決めて行動することも進捗状況を把握し、業務を効率よく進めるには大変有効です。
そして、作業をしていると、当前のことながら、疲労がたまります。疲労が蓄積したまま無理に作業を継続すると、効率が落ちてしまいます。1時間働いたら5分休憩するなど、適度に休みをはさむことで、結果的に業務効率アップにつながります。
2. 業務効率化に役立つツールやサービス

現在、業務効率化に役立つ便利なツールが数多く存在します。正しく使いこなすことで、日々の業務効率アップに貢献してくれるビジネスツールをご紹介します。
コミュニケーションツール
コミュニケーションツールとは、パソコンやスマートフォンなどを通じて、複数人とリアルタイムでメッセージのやり取りができるチャットツールや、音声通話機能ツールの総称です。
チャットは、情報共有をよりタイムリーに行いたい場合に、とても有効な手段となります。短いテキストのやり取りを通じて、コミュニケーションできるのが特長です。最近では、ビジネスシーンに対応した社員間でのみ利用可能な社内チャットや、クライアントなど外部ともやり取りできるビジネスチャットなど、さまざまなものがあります。
- Slack
- チャットワーク
- LINE
(LINE WORKS) - Facebook
(Workplace)
スクリーンショットツール
スクリーンショット(スクショ)とは、PC画面のキャプチャ画像を撮影できる機能のことです。自分が見ている画面をそのまま切り出すことができるため、情報共有や資料作成に活用できます。また、長いページを自動でスクロールして撮影してくれるものや、撮影した後の加工をサポートしてくれる機能がついているツールもあります。
- Winshot
- SnapCrab for Windows
- Screenpresso
オンラインストレージサービス
オンラインストレージとは、インターネット上にデータを保管するサービスで、クラウドストレージとも呼ばれています。用意された保管場所(ストレージ)に、利用者はファイルを保存します。クラウド上にファイルを置いているため、複数のPCやモバイル端末からデータにアクセスすることができます。1つのファイルを複数人で共有して、リアルタイムで閲覧・編集することも可能です。
- Dropbox
- Googleドライブ
- box
- Microsoft OneDrive
タスク管理サービス
タスク管理サービスは、手持ちの業務タスクを可視化してくれます。作業の進行状況を把握できるサービス、ToDoリスト化するサービス、Web上のカレンダーに表示するサービスなどさまざまです。日々のタスクが多くて優先度が分かりにくい、対応漏れが発生するなどの課題を抱えている場合におすすめです。業務全体のボリュームやタスクの優先順位などを把握しやすくなります。
- Backlog
- Trello
- JIRA
RPAツール
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ロボットを活用して業務自動化を行うソフトウェアツールです。入力値のチェックや合計金額の照合など、割合単純な定型業務であれば完全に自動化することができ、例えば、手作業で行っていた請求書の処理作業などの業務効率化につなげることができます。またロボットによる自動作業となるため、人間が行うよりもエラーやミスが発生しにくいというメリットもあります。
- UIPath
- WinActor
- BizRobo!
オンライン会議システム
オンライン会議システムは、PCやタブレット端末、スマートフォンなどを用いて、オンライン上で会議を開催できるシステムのことです。国内のみならず、海外拠点との会議にも活用でき、移動時間を節約して業務効率化に大きく貢献するツールです。特にコロナ禍でテレワークが急速に増えてからは、在宅ワーカーやサテライトオフィスワーカーとの間でもスムーズに会議ができることで注目が集まりました。
- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams
勤怠管理ツール
勤怠管理システムとは、手作業で行うと手間がかかる勤怠管理を自動化し、システム上で社員の出退勤時間や休暇日数などを管理できるシステムです。勤怠管理の自動化により、煩雑な給与計算など労務担当者の負担を軽減します。また、近年、変化している労働基準法に照らして、従業員の働き方を把握するにも役立ちます。
- ジョブカン
- KING OF TIME
- jinjer勤怠
SFAツール
SFAとは「Sales Force Automation」の略で、日本語では「営業支援システム」と訳され、営業スタッフの行動を管理し、効率化することを目的としたシステムです。最近では、他のシステムと連携することで営業現場の入力の負荷を軽減し、ナレッジを共有するツールとしても活用されています。
- Sales Cloud
- Senses
CRMツール
CRMは「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」の意味を持ち、お客様に関連する情報を管理し、そのデータを活用して売り上げアップを狙うことを目的としています。顧客情報・営業情報をデータ化し、情報の共有・分析・管理に役立ちます。
- Kintone
- Oracle CRM
マーケティングオートメーション(MA)ツール
マーケティングオートメーション(MA)ツールとは、収益の向上を目的として、マーケティング活動を自動化するツールです。MAを導入することで、顧客情報を一元管理でき、顧客の興味・関心の状態に合わせたアプローチや施策が行え、業務効率を大幅にアップすることができます。
- Marketo(マルケト)
- Salesforce Pardot
- SATORI
ワークフローシステム
ワークフローシステムとは、業務の流れに関連する申請や承認手続きをデジタル化するシステムのことです。ワークフローシステムを利用することで、業務手続きがオフィス外でも可能となり、紙の申請書を提出するための出社も不要です。また、決裁までの状況も可視化され、申請者や管理者はどこまで進んでいるのかも把握できます。最近では、可視化できるという利点を活かし、改ざん防止や早期の不正発見を目的にして、ワークフローシステムを導入する企業も増えてきています。
- rakumo
- kintone
電話自動架電システム
上記でご紹介したツールやシステムを導入して活用するには、部署やチーム全体の協力があってはじめて成立するものが多いですが、システムを導入して、簡単な設定を行うだけで業務効率につながるシステムもあります。代表的なものが、電話自動架電システムです。
電話自動架電システムは、特定のアドレスからのメールや、あらかじめ指定したキーワードを含むメールを受信した際に、電話を鳴らして受信を知らせるというシステムです。重要なクライアントからのメールや、急ぎの要件を含むメールを埋もれさせず、確実に受信状況をキャッチアップできるのが特長です。
具体的な電話自動架電システムとしては、「急コール」が挙げられます。「急コール」は1分間隔でメールの有無をチェック。件名や本文に指定のキーワードが含まれているメールを抽出し、音声アナウンスを使用した架電を行います。対象となるメールを発見してからの時間は、最短で15秒。スピーディーなお知らせが可能です。
なお、架電先の担当者が電話に出られない状態であれば、決められた順に次の担当者へと電話を自動的に回します。また、音声アナウンスによって対応の可否を質問し、電話を受けた担当者はボタンプッシュで回答することも可能です。
架電結果はシステム上で確認でき、どの架電先担当者が応答したかなどのチェックもできます。さらに、そのデータを蓄積して、業務が忙しい曜日や時間帯がわかっている場合には、あらかじめその担当者に電話を回さない、その時間帯だけサポートのメンバーを増やすなどして、会社全体での業務効率化を図る検討ができるようになります。
- 急コール
3. 業務効率化するときの注意点

業務効率化は、しっかり検討した上で行わないと、余計な作業やコストを発生させてしまい、本末転倒になってしまうということもあるようです。業務を効率化する際に注意すべき点を下記でご説明します。
手間やコストが増える
単にシステムやツールを導入しても、実際の現場環境にマッチしていない場合は、余計に手間が増えるということがあります。そして、無理に使用することでミスを連発したり、逆にシステムやツールを使わずにコストだけが増加したりすることもあります。
また、業務委託やアウトソーシングなどで社外の人材・サービスを活用する場合も、指示伝達が充分でないと、行ってほしい作業をやってもらえなかったり、さらには大きなミスに発展してしまったりする場合もあります。ミスやクレームが発生すると、その対処に追われ、結果として業務効率が低下してしまうので、注意が必要です。
業務効率化は検証することも大切
業務効率化のツールなどを導入した後は、期待した効果が実際に出ているかを検証することが重要です。検証の際は「PDCAサイクル」と呼ばれる方法が有効です。「計画(Plan)」→「実行(Do)」→「検証(Check)」→「改善(Action)」の一連の流れを繰り返して検証精度を高めましょう。
検証を始める前に、まず何を目的として改善を行っているのかを明確にし、その指標を基準に、業務効率化の前後でどう変化したかを記録します。指標の一例としては、以下のものが挙げられます。
| 時間 | 各工程の作業時間や残業時間 など |
| コスト | 人件費や設備費の増減 など |
| 品質/精度 | ミスの発生数 など |
| 付加価値 | クレーム件数減 など |
4.「急コール」で業務効率化!メールを受信したら電話でお知らせ
ここまでさまざまな業務効率化のアイデアをご紹介してきました。現在の業務と照らし合わせ、何を行えば業務効率化になるのかを検討してみてください。
即効性の高い施策としては、緊急性の高いメールを受信したら、すぐ電話で通知する電話自動架電システム「急コール」の導入をおすすめします。電話とメールはどの業態にも欠かせないビジネスツールです。双方の利点を組み合わせることで、クライアントニーズを取りこぼしません。
「急コール」では1分間隔でメールの有無をチェックし、既定のキーワードが含まれているメールを抽出することができます。対象となるメールを発見してから最短15秒で、音声アナウンスを使用した架電を開始します。メインの担当者が電話に出られなければ、別の担当者へと順に電話を回すことも可能です。
また、架電結果はメールとWeb画面上のマイページで確認できます。どの架電先担当者が応答したのかなど、状況をチェックすることも可能です。
特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」
詳しくはこちら

 03-5829-4886
03-5829-4886