メール見落とし対策|メールの見落としを防ぎ、気づかないを解消する方法をご紹介

日々の業務に追われ、重要なメールを見落としてしまうことに悩んでいませんか?
・監視システムの障害アラートメール
・取引先からのクレーム連絡とエスカレーションメール
・経理からの支払い条件変更の通達
これらを見逃してしまうと、サービス停止や納品遅延、与信リスクの発生に直結します。たった1通のメールの見落としが、重大なトラブルや信頼失墜につながることも少なくありません。
本記事では、メール見落としの主な原因と具体的なトラブル事例を整理し、メールに気づく方法(通知/優先度/仕分け/検索)やメール見落とし対策(Gmail・Outlook設定)、再発防止の仕組み化までを網羅的に解説します。
メールの見落とし防止ツールの活用ポイントも取り上げ、実務で“メールに気づかない”を減らす具体策を提示します。
目次
- メールを見落としたことで発生したトラブル事例
- システムダウン!真夜中のサーバー監視業務でトラブル
- メールの見落としでまさかの失注!
- 社内評価ダウン!あのメールさえ見ていれば…
- メールを見落とす原因
- 確認・返信の時間を確保していない
- メールが多く整理できていない
- 後回しにしてしまう
- メールを見落としてしまった場合には、電話やメールで謝罪の連絡を
- メールの見落とし防止対策
- メールを分類する(フラグ付け・ラベル分け)
- フォルダー分けをする(Gmail・Outlook)
- ツールを活用する(“確実に気づかせる”仕組みの導入)
- 「急コール」を利用したメール見落とし対策
- 特定メールの受信を電話で通知する「急コール」とは?
- メールから自動で電話をかけるリアルタイム通知
- 担当者の「対応可」回答を取得し、対応結果も把握できる
- 運用に合わせた設定が可能
- 急コールの導入事例
- まとめ
1. メールを見落としたことで発生したトラブル事例
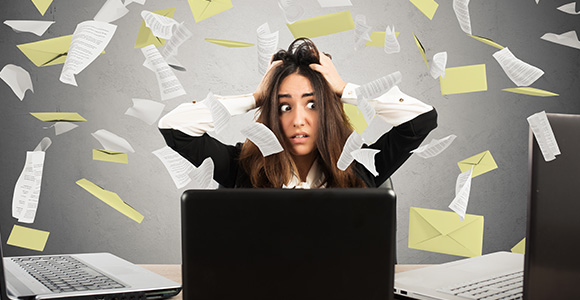
まずこのセクションでは、メールを見落とした/気づかなかったことで実際に起きたトラブルを、代表的な3つのケースで解説します。障害アラートの未読、問い合わせメールの埋没、社内通達の見落としという“起こりがちな原因”と、サービス影響・失注・評価低下といった具体的な損失を整理します。
システムダウン!真夜中のサーバー監視業務でトラブル
深夜帯の障害対応は、たった1通のメール見落としがサービス影響に直結します。
本事例では、障害アラートメールに気づけず初動が遅延。夜間バッチやデータ転送が止まり、翌朝まで影響が波及しました。
- 24時間365日で運用されるサービスで、深夜帯は在宅オンコールの最小体制での監視体制
- 障害発生時、監視ツールからのアラートメールは送信されたものの、メールクライアントの自動仕分けで下層フォルダーへ移動し、端末の集中(おやすみ)モードにより通知も鳴動しなかった
- 当番者は重要メールに気づかないまま朝まで未読となった
これにより、以下のようなメール見落としの影響が発生します。
- 夜間バッチやデータ転送が停止・遅延
- 臨時対応コスト増・売上機会の逸失が発生
メールの見落としでまさかの失注!
新規見積依頼や問い合わせがポータル経由でメール通知される運用では、競合より早い初動が受注率を左右します。
本事例では、受信後約1時間気づかないまま対応が遅れ、問い合わせ案件の失注に繋がりました。
- 問い合わせ通知はメールのみ
- SFA/CRMへの自動登録やチャット連携は未実装
- 会議や顧客対応など、他の業務に集中しており、受信時にメールクライアントを見ていなかった
これにより、以下のようなメール見落としの影響が発生します。
- 初動の遅れにより競合が先行対応 → 案件失注
- 見落としが重なると既存顧客の信頼低下や解約・取引中止のリスクに波及
社内評価ダウン!あのメールさえ見ていれば…
社内でも、稟議の差し戻し、仕様変更、締切前倒し、シフト調整、セキュリティ通達などの重要連絡が日々メールで届きます。本事例では受信メールが多すぎて、優先タスクの判断を誤りました。
- 社内周知はメール中心で、Teams/Slack・電話などへの多重通知は未連携
- メーリングリストや全社一斉配信、過剰なCC/BCCで受信量が過多となり、重要メールがタイムライン上で埋没(未読が積み上がる)
これにより、以下のようなメール見落としの影響が発生します。
- 優先タスクの入れ替え遅れにより納期遅延や手戻りが発生
- 上長・関係部門からの信頼低下、評価減やアサイン縮小・昇格見送りに波及
2. メールを見落とす原因

万が一メールを見落とすと、顧客クレームの発生、社内評価の低下、対応遅延による案件の失注といった重大な損失につながりかねません。では、なぜ“メールに気づかない/見落としてしまう”のでしょうか。下表で主な原因を整理し、今日から実践できるメール見落とし対策と再発防止のポイントを示します。
(表:メール見落としの原因と対策)
| 原因 | 具体的な症状・リスク | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 確認・返信の時間を確保していない | 未読が積み上がる/朝夕の“一気読み”で重要メールを取りこぼす/一次応答が遅れる | ・スケジュールを組み、メールの確認・返信を習慣化する |
| メールが多く整理できていない | ML・全社配信・過剰CCで重要が埋没/仕分けで下層に流れて気づかない | ・送信者や案件ごとにルールを作り自動振り分けをする ・不要なメルマガを配信停止する |
| 後回しにしてしまう | 開封済みなのに未対応のまま忘却/二重対応・期限超過の発生 | ・数分で返せるものはその場で即返信するなど対応のルール決め ・定型的な問合せにはテンプレを使用する ・チケット化して、担当・期限・進捗を管理する |
以上のとおり、メール見落としの主因は「時間を確保していない」「受信量に対して整理が追いつかない」「確認後に後回しにして忘れる」の3つに集約されます。
とはいえ、対策を講じても確認不足や対応の遅れを完全にゼロにはできません。万一見落とした場合は、まず電話またはメールで迅速に謝罪と状況説明を行い、対応方針と期限を明確に伝えることが被害拡大を防ぐ最善策です。
続くセクションで、具体的な手順を解説します。
3. メールを見落としてしまった場合には、電話やメールで謝罪の連絡を

万が一、メールの見落としが発生した場合、できる限り迅速かつ誠実に謝罪の対応をすることが大切です。誠意を持ってスピード感のある対応をすれば、顧客が自社に対してマイナスな印象を抱くことを最小限にできるでしょう。以下では、メールの見落としがあった際の、お詫び文例を紹介します。
○○株式会社
営業部 ○○様
いつも大変お世話になっております。
○○株式会社の○○です。
○月○日にお送り頂いたメールに関して、ご連絡が大変遅れてしまい申し訳ございません。
私の不手際により、○○の対応に関して遅れが生じてしまい、○○様には大変ご迷惑をお掛けしました。
つきましては、○○に関して早急に対応させて頂きますので、今しばらくお待ち頂けますと幸いです。
進展について、○月○日までには必ずご報告致します。
今後は二度とこのような不手際を起こさぬよう
誠心誠意努めて参ります。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
(署名)
場合によっては、メールを送信する前に、お詫びの電話を入れておいた方が良いでしょう。メールと電話で併せてお詫びの気持ちを伝えることで、相手の印象が変わることを期待できます。
4. メールの見落とし防止対策
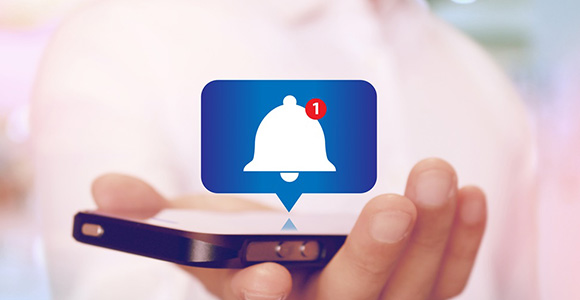
ここからは「メールの見落とし防止対策」を考えます。
先に整理した原因を踏まえ、メールに気づく方法(通知・優先度・仕分け・検索)の見直し、GmailとOutlookフォルダー設定、見落とし防止ツールの活用まで、今日から実践できるメール見落とし対策を具体化します。ポイントは、確認不足と対応の遅れを仕組みで減らし、運用に定着させることです。メールを見落とさない方法をステップで解説し、再発防止までつなげます。
メールを分類する(フラグ付け・ラベル分け)
未読・既読などメールの対応状況や重要度に応じて、フラグ付け、色ラベルによる分類を行うと良いでしょう。目で見てはっきりとメールの性質が把握できるため、業務の効率化へと繋がります。
代表的なメールサービスとして、GmailとOutlookの色ラベルやフラグ付けなどを紹介します。例えばGmailでは、「その他アイコン」から「ラベルの色」を選択すれば、色ラベルのカラーを自分で設定可能です。一方、Outlookでは、カテゴリーの項目からグループ別に色を選べます。
また、Outlookではカテゴリー項目の横にフラグ付けの項目もあるため、必要に応じてチェックを入れられます。Gmailはフラグの代わりに、重要なメールに対しては重要マークを2種類から選べるため、活用すればメールチェックを簡素化できるでしょう。
フォルダー分けをする(Gmail・Outlook)
送信元に応じてフォルダー分けしておくことで、大事なメールが埋もれる可能性を減らせます。GmailとOutlookを例に、メールフォルダーの作成方法についてそれぞれ紹介します。(※2025年9月時点の情報です)
■Gmailのメールフォルダーの作成方法(PC版)
- 1. Gmailの画面左にある「もっと見る」の項目をクリック
- 2. 「新しいラベルを作成」の項目をクリック
- 3. ラベル名を入れて、「作成」ボタンをクリック
- 4. 画面右上にある「設定」(歯車のアイコン)を選択し、「すべての設定を表示」の項目をクリック
- 5. 「フィルタとブロック中のアドレス」を選択し、「新しいフィルタを作成」の項目をクリック
- 6. 「To」の項目に受信するメールアドレスを入れて、「フィルタを作成」ボタンをクリック
- 7. 「ラベルを付ける」の項目で、任意のラベルを選択し、「フィルタを作成」の項目をクリック
※もしくは、検索バーの検索オプション(スライダー)を開き、条件入力→「フィルタを作成」でも行えます。
■Outlookのメールフォルダーの作成方法
- 1. Outlookの画面上の「受信トレイ」の箇所で右クリックを行い、「フォルダーの作成」の項目を選択
- 2. 受信トレイに作成されたフォルダーの名前を、任意の名称に変更
- 3. Outlookの上部のタブから「ホーム」を選択し、「ルール」の項目をクリック
- 4. 「仕分けルールの作成」の項目をクリック
- 5. 表示されたダイアログボックスの「差出人・件名・宛先」などの項目を設定
- 6. 「アイテムをフォルダーに移動する」にチェックを入れ、「フォルダーの選択」ボタンをクリック
- 7. 振り分けたいフォルダーを選択し、「OK」ボタンをクリック
- 8. 「現在のフォルダーにあるメッセージにこの仕分けルールを今すぐ実行する」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリック
ツールを活用する(“確実に気づかせる”仕組みの導入)
フラグ・ラベルやフォルダ分けは基礎として有効ですが、どれも“こちらから見に行く”前提の受動的対策です。会議・外出・在宅の集中モード、共有メールボックスの受信過多などでは、これだけでは確認不足や対応の遅れを完全には防げません。
そこで、重要メールの到着をトリガーにアラートを発報するメール見落とし防止ツールの出番です。
重要なメールを「差出人/件名/本文キーワード/時間帯等」で分類し、それをメール以外の方法で再通知(電話・音/SMS)、までを自動化すれば、「気づかなかった」を仕組みで潰せます(Gmail/Outlookとも連携可)。
次のセクションでは、電話発報で確実に知らせる「急コール」を使ったメール見落とし対策を具体的に解説します。
5. 「急コール」を利用したメール見落とし対策
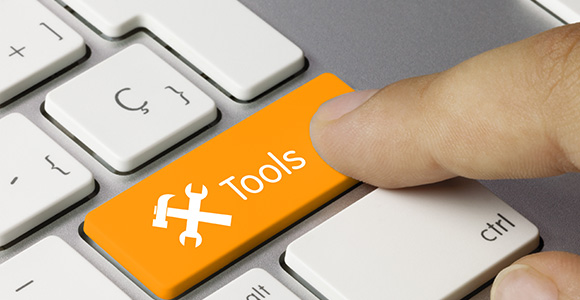
ここからは、メールの見落とし防止に効果的な「急コール」を活用した対策を、具体的に紹介します。
特定メールの受信を電話で通知する「急コール」とは?
「急コール」は、受信メールの件名と本文を自動判定し、条件に合致した特定の重要メールだけを対象に、音声ガイダンスで自動架電して確実に知らせるクラウドサービスです。メール中心の受動的な運用で起こりがちな確認不足や対応の遅れを、“電話で気づかせる”仕組みで最短に抑えます。
(急コールの処理フロー)
- メールの件名と本文をフィルタリングし、キーワード合致メールを抽出
- 指定共有先に受付メール/SMSを送信(架電先担当者にも送信可)
- 架電先担当者に自動で電話通知(一斉架電または順次架電)
- 架電先担当者からのボタン選択による回答を取得(「対応可」以外の回答にはリトライ架電)
- 指定共有先に架電処理結果メール/SMSを送信
「急コール」の特長やメリットをご紹介します。
メールから自動で電話をかけるリアルタイム通知
「急コール」の利点は大きく二つあります。第一に、受信メールの件名・本文(必要に応じて差出人)を自動判定し、重要なものだけをフィルタリングできること。第二に、条件に合致した場合に担当者へ自動的に電話連絡(音声ガイダンス)し、確実に気づかせることです。
この動作の基本単位が「架電パターン」です。受信用メールアドレスと発信用の050番号を1セットとして扱い、1パターンあたり架電先電話番号を最大32個まで登録可能。さらに、メールをフィルタリングするキーワードは最大20個設定でき、通知対象をきめ細かく絞り込めます。
自動化することによって電話対応する人件費も最小限に抑えられるとともに、タスクが多く忙しい場合でも対応せずに済むため、ヒューマンエラーも防ぐことが可能です。
見落としを防いで初動対応が早まることが、「急コール」導入の大きなメリットです。
担当者の「対応可」回答を取得し、対応結果も把握できる
架電の結果は、指定共有先のメールアドレスへ送信されます。そのため、誰が対応を行うかといった対応結果を確認できるとともに、誰でも時間を問わず状況を把握できます。メールアドレスは複数登録できるため、幅広い状況共有も可能です。
見落としを防いで対応結果を把握できることも、「急コール」の大きな特長です。
運用に合わせた設定が可能
電話の呼出時間の設定や、他に担当できる人がいない場合のリトライ設定の回数も設定できます。また、電話対応の可否は、対応可能であれば「1」、対応不可であれば「2」をプッシュするだけで良いなど、社内体制に合わせた運用を実現するために自社独自で設定ができるので、電話を受ける担当者側の負担も大幅に軽減できます。
また、電話番号登録のシフトは2パターンまで登録できるため、例えば日中対応と深夜対応のグループを分けたい場合にも便利に使えます。
急コールの導入事例
それでは、実際に「急コール」を取り入れて業務改善を行った事例を見ていきましょう。
BtoBtoC市場における企業向け会員制アウトソーシング事業を担われている、株式会社JTBグローバルアシスタンス様では、海外へ渡航されるお客様の安全を24時間365日サポートする受託業務を行っています。
危機やリスクといったそれらの情報の中には時差がある海外発信のものも含まれ、日々休みない情報収集が不可欠で、かつ、収集した情報の内容を迅速に把握し、危機管理方針の判断から実行といった業務を速やかに遂行するため、メール監視が必要でした。担当者はそれをアラートにして定期的にメールをチェックするのですが、見落としてしまうリスクを限りなく回避できる方法を模索していました。
そこで「急コール」を導入した結果、「メール見落としのリスクを最大限に避ける」という最も課題に感じていた点がクリアになっています。
また、導入後は以前のしくみよりも対応が迅速になり、使い勝手も良く、非常に低コストで導入が可能だった点にもご満足いただけたとのことです。
>旅行、物流、不動産…様々な業種で急コールをご活用いただいています。事例の一覧はこちらから
6. まとめ

メールの見落としを防ぐ基本は、フォルダー/ラベル運用と確認・返信時間のブロックなど日々の運用設計です。これらを徹底すれば、確認不足や対応の遅れは確実に減らせます。とはいえ、会議・外出・在宅の集中モードなどでは受動的な対策だけでは限界があり、見落としが続けば失注やクレームなどの事業リスクに直結します。
「急コール」を導入すれば、既定のキーワードを含むメールを抽出し、担当者に自動的に電話連絡をしてくれます。メールの見落としを防ぎ確実な対応ができるだけではなく、これまで連絡対応に割いていた人件費削減の効果も期待できるでしょう。また、Web画面上で設定・管理できるため、インターネット環境があればどこでも簡単に利用できます。
メールに気づく方法を強化し、再発防止まで一気通貫で整えたい方は、まずは「急コール」で運用課題と効果を確認してみてください。無料トライアルもご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」
詳しくはこちら
※機能や価格は公開日時点の情報です

 03-5829-4886
03-5829-4886